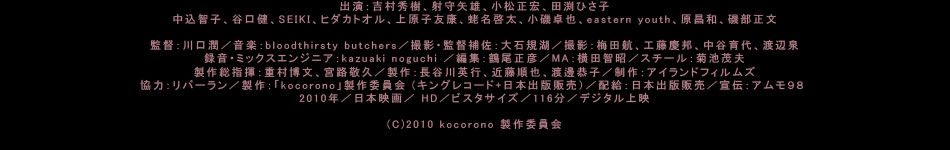―KO SLANG (SLANG / KLUB COUNTER ACTION)
17歳ぐらいのときかな?それまでも怒髪天やSCANNERS(イースタンユースの前身バンド)は観に行ってたんだけど、「PUNK NITE」ってイベントで「畜生のボーカルの新バンドが出る!」って聞いてね。ワクワクしながら観に行ったんだよ。そしたらそのイベントの最後にブッチャーズが出て来てね。畜生ってすごいメタリックなハードコアで、みんなも当然それ期待してたと思うんだけど、音がぜんぜん違ったんだよね。映画でもそのデビューライブの映像使われてるけど、眉毛とか無くて見た目はおっかないのに曲はけっこうポップでさ、いい意味でもの凄い裏切られた。それともう一つ衝撃だったのが、札幌のおっかない先輩たち、ブッチャーズの曲にあわせて輪になって踊ってたんだよね。それも凄い衝撃的でさ。当時はパンクのライブ=バイオレンスみたいなところあったのに、凄い平和的な光景だったんだよ。床にはガチャガチャにグラスとか割れててさ、暴動の後みたいな光景の中でね。おれは15歳から札幌のライブハウスに通うようになったんだけど、中学生ぐらいの頃は正直「とりあえず札幌でバンドの下地作って東京へ!」みたいな部分もあったんだよね。だから大袈裟じゃなく、おれの運命を決定的に変えた日だったんだ。その日が人生でいちばんの転機だった日かもしれない。そのライブが切っ掛けだったからね、おれが札幌で死ぬまでやって行くって決めたのは。
―TAYLOW/the原爆オナニーズ
bloodthirsty butchersの映像が出来た。これは快挙です。能書き垂れる前に、ブッチャーズの記録を凝視する。瞬間にメンバー間で勝負している。お互い何をやりたいのか、つかみとって、表現する。バンドって、空気なんです。
―奈良美智
幻想を破壊するように軌跡があり、たとえ廃墟になっても鳴り響く音がある!
―横山健
人生の中にどう音楽を置くのか…、音楽で生きていきたい者にとっては切っても切れない大きなテーマが、バンドという集合体を捕えた向こうにくっきりと浮かぶ。生々し過ぎて辛いが、目をそらせなかった。
―あがた森魚(歌手)
俺と同じく北海道の留萌で生まれて北海道で育ったバンドらしいことが、映画を見てわかった。映画を観た後、しばらく夜道を一人で歩きたくなった。彼らの歌いたいことや言いたいことや欲張りたいことが自分と似てるような気がした。俺は一人で歌う歌手だから、バンドでやってることがうらやましく思えた。言いたいことを最後に言いあえる仲間がいるってことはすごいことだ。ブッチャーズはそれをやれているからな。
―森直人(映画評論家)
紛れもなく『メタリカ:真実の瞬間』『ピクシーズ/ラウド・クァイエット・ラウド』を引き継ぐロック“バンド”ドキュメンタリーの傑作。そして、いまをタフにサヴァイヴするために必要なココロノ名作!
―浅野忠信
バンドが持つ未完成でいいのだという力に打ちのめされました。これを知ってると楽しいです。
―樋口泰人(boid主宰)
若さからも老いからも微妙に見放された男たちがそこにいる。つまりロックという物語から体よく見捨てられつつある男たち。庇護幕が取り払われたむきだしの世界の荒涼に、彼らの音楽は鳴り響く。生きる場所はそこだ。音楽が生まれる場所もそこだ。その始まりの場所を、この映画は映し出している。もちろんその場所は、私たちにとっての始まりの場所でもあるだろう。
―中込智子(音楽ライター)
「わかってたまるかバカヤロー!」ブラッドサースティ・ブッチャーズ、吉村秀樹のかつての口癖だ。自分達の音楽に込められた自身の複雑な感覚感情について、軽々しく「わかった」などと言ってもらってはたまったものではない、という気持ちがあったからだと思う。そこで私は「よくわからないんだけど、それはどうゆうこと?」という聞き方をするようになった。すると吉村は言った。「姉ちゃんはわかろうとする気持ちが足りないんだよ、もっとわかってよ!」…どないすれっちゅうんじゃ、と思ったものである。いや、念のために言うと吉村はいつでも精一杯誠実に対話に臨んでくれた。ただ常に、わかったと言えば「わかってない!」と答え、わからないと言えば「わかれ!」と答える難儀な男だったのだ。それは、本当はわかって欲しいと願っている天の邪鬼な男の正直な本心であったと私は思う。ブッチャーズ初となるドキュメンタリー映画『kocorono』には、そんな吉村秀樹のリアルな姿、つまり難儀っぷりが、もう余すところなく赤裸々に綴られている。当然起こるメンバーとの対立、きしみも、容赦なくそのまま映し出されていく。正直、場面は緊迫に次ぐ緊迫であり、思わず息を詰め、汗をかいてしまった両手をぐっと握りしめながら身を乗り出して見入ってしまう場面も多い。序盤はごく短い尺で数多く、後半に行くに連れ腰を据え、じっくりと挟み込まれる新旧取り混ぜた演奏シーンの迫力も凄まじい。こうした場面を積み重ねた上で生み出された音楽、演奏なのだと知った上で観、聴くと、それでなくとも凄いと思っていた楽曲に、さらに肉感が大増して響くのだ。私は以前ブッチャーズを評し、『パンクやNWが彼らの出発点だったことは確かにわかる。ジャンクやグランジ、さらにはエモに通じる部分を持っていることも確かだ。だが、彼らの楽曲にはそれらの全てがありながら、それらのどれでもなく、かといってそれらのクロスオーヴァーでもない。国内外を通じてどこにも存在し得なかった、他の追従を許さない完全独自のオリジナリティがここにあるのだ。それも、とても美しいメロディーを伴って?』と書いた。当時は「おっしゃあ!」と思ったものだが、今思えば我ながら、わかっていたようでわかっていなかった。大事なことは、そこじゃない。この映画を見れば、それがわかる。いや、やはりわかった気になっているだけなのか?とにかく、よくぞここまで写し取ったというシーンの数々。116分という2時間近い時間がアッと言う間に過ぎ去っていく本作は、まさに起承転結のない、真のドラマだ。バンドを、音楽を愛する全ての皆さんに、どうか観ていただきたいと心から思う。感動という言葉ではとても納まり切らない、心の震えと強烈な余韻を約束します。